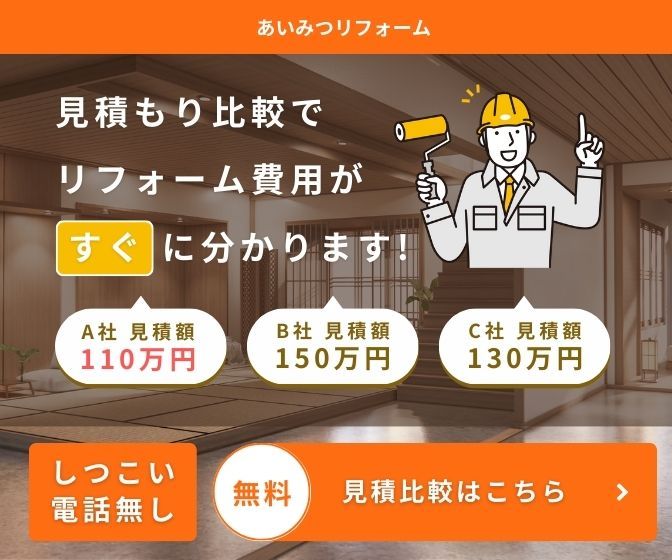65歳以上で、貧困率が年々増加しています。現在の年金では不足している実情があります。
特に現在は、単身の高齢者が増加して、別に暮らしている子ども世帯からの援助がない状況です。
2018年の公的年金の受給の平均額は、65歳以上の男性が月額約17万円前後、女性が月額約11万円前後でした。
この金額も年々減少しています。夫婦で年金をもらえれば、とりあえずやっと暮らしていけますが、そうでない単身世帯は、生活が苦しいのが実情です。
とりあえず、自己防衛を図っていかねばなりません。
本日は、自高齢者の住みやすように、家のリフォームをする話です。
〇本日のテーマ 介護 リフォーム 補助金
〇記事の信頼性
記事を書いている私は、心理学分野で博士号を取得しています。
〇読者への前置き
精神医学と心理学の二方面から人間関係を困難にする状況をゆっくり解説します。
介護リフォーム
介護リフォームのための住居改築は、介護保険の制度の中に含まれます。要介護・要支援者の生活の安全にするためだからです。
上限20万円まで補助金が出ます。住宅改修の補助金は原則1回しか使用できませんが、限度額内ならば、分けての利用も可能です。
また助成金制度がある自治体もあり、受け取れる額を把握しておくと負担を軽くすることができます。
転倒 骨折
自宅での転倒・転落による高齢者の方が骨折などをする怪我をする事故は多いです。
サルコペニアに陥った人、さらに認知機能の低下した高齢者では、少しの段差や階段などでも転倒・転落の危険性があります。
高齢者の転倒事故の約80%は居宅で起こっています。そのため、バリアフリーが大切です。
転倒は起こるものとの前提のもと、住環境を整える必要があります。
では、いつバリアフリーなどを検討すればよろしいでしようか?
よく、言われていることが要介護の認定を受けたときとされます。
事故が起きる前は、必要ないように感じるかもしれませんが、事故が起きてからの検討は時期を失することになります。
そこで、補助金や助成金を視野に入れながら、検討をするとよいと思われます。

リフォーム支援金
リフォームは、「介護保険の補助金」と「市区町村の助成金」の2つがあります。
介護保険 補助金
介護保険の補助金は、要支援・要介護の認定が条件です。
介護保険は、40歳から加入が義務付けられています。
介護の必要から住宅改修費も、介護保険から補助してもらえることが可能です。
住宅改修費における自己負担は、介護保険制度における自己負担割合1割から3割です。
要件 条件
住宅改修費の支給を受ける条件は、
「利用者が要介護認定で要支援・要介護の認定」
「改修の住宅が介護保険被保険者証の住所と同じ」
「利用者が住んでいる」
「入院・福祉施設入居等で自宅から出ていない」
「以前に住宅改修費の上限までの支給を受けていない」です。
住宅改修費は、介護サービスの区分支給限度額とは別枠での支給になります。うまく利用してください。
また、居宅の変更をした場合(引っ越し等)、要介護度が3以上になった場合は再度支給を受けられます。
繰り返しになりますが、住宅改修費の補助は、上限額はありますが分割して利用もできます。
支給方法
介護保険の住宅改修費の補助金は、最大20万円分の工事費です。
最大20万円の中に自己負担額も含まれ、自己負担割合で違ってきます。
目安として、1割負担の場合ならば最大で18万円、3割負担の場合であれば14万円が最大の補助金として支給されます。
利用者が全額支払った後で自治体から補助金が支給されます。このような方式をとるため、一時的に費用を用意しなければなりません。
しかし、自治体によっては申請して、あらかじめお金をもらえる所もあります。確認をしてください。
利用者が自己負担額分(介護保険)だけを支払い、残額は自治体から直接業者に支払います。
リフォーム補助制度
介護保険適用のリフォームは、20万円を超えると支給対象になりません。
ただ、自治体によって住宅改修補助制度が存在する場合もあり、上限を超えも補助金が受けられる場合もあります。問い合わせをしてみましょう。
リフォーム 手続の方法
介護リフォームの際に補助金支給を受ける手順は以下の通りです。
①要介護・要支援の認定を受ける
②担当となるケアマネジャーに改修の相談を行う
③施工業者とケアマネジャーの同席で打ち合わせ
④契約する事前申請の書類を自治体に提出
⑤審査結果を確認する
⑥着工する
⑦利用者が一時的に全額を支払う
⑧リフォーム完成の後に自治体同じように申請する
⑨住宅改修費を受け取る
必要な書類は以下の通りです
介護保険被保険者証
住宅改修内容の書類
改修場所や費用見積の申請書
改修前の状態の写真
ケアマネジャーの作った住宅改修理由書
施工業者の作った工事図面や工事費見積書
領収書や工事費内訳書
改修の後の写真
申請で留意点は、工事の前と後で2回行うという点です。。
改築後は、領収書や改修後の状態の申請を出さねばなりません。
適用できる工事の種類
保険適用になるものは、6種類です。
①「手すりの設置」
②「床段差の解消」
③「滑り止めの防止・移動の円滑化」
④「扉の取り換え」
⑤「様式トイレへの便器の取り換え」⑥「①から⑤に必要となる改修」

手すりの設置
介護生活の中で、転倒の防止、立ったり座ったりするのに使います。
立ち上がりに必要な玄関・トイレ・風呂、転倒しそうな階段に設置されます。
また、それ以外の段差の個所なども転倒の危険があれば設置できます。
床段差の解消
高齢になると、思うように足が上がらなかったり、認知症に陥ると、少しの段差にもつまづきやすくなります。
そのため段差そのものをなくす工事にも適用できます。敷居を低くする、スロープを設置、床のかさ上げです。
滑り止めの防止・移動の円滑化
床材によっては滑りやすく、転倒する場合もあり、床材そのものをかえたり、クッションフロアはったりできます。浴室の床をすべりにくくするなどです。
扉の取り換え
腕の筋力が弱まり、また、手先が不自由になった場合には、自宅の扉やドアをかえる工事ができます。
例えば、引き戸などにドアを変えたり、アコーディオンカーテンにかえる、ドアノブの変更、戸車を付ける、引き戸を新しくする等々です。
洋式便座等への便器の取り換え
和式便所はしゃがんで立ち上がるの動作が必要なので、転倒や膝を痛めたりします。そこで、洋式便座へのリフォームがあります。
トイレの位置を変えて、広場を少し作って、介護しやすいようにすることもありましよう。
本体工事と、その前の予備工事(下地工事)も、あわせて補助金がでます。
市区町村 助成金
自治体の助成金制度は、支給条件等がそれぞれ違い、問い合わせと確認をしてください。
介護保険の補助金より額が多かったり、6種類以外の工事にも助成金が出る場合も考えられます。
ただ、市区町村の助成金制度は、受給の条件が難しいとされています。
また、市区町村の中には、介護保険の補助金を受けている場合は、受けられないというところもあります。
リフォームをするときは、まず見積もり比較をして、費用の面を考えることが大切です。