
回想法では、「自分の過去」を話し、自分の昔の写真や思い出の物などを見返し、過去の記憶を鮮明に思い出します。
このことにより自分を見返し、自分が生きている意義をもう一度見出します。
一対一、グループで行うものがありますが、周りの人があたたかく接することで、安心感を得て、自信を取り戻すことにつながります。
〇本日のテーマ 高齢者 回想法
〇記事の信頼性
記事を書いている私は、心理学分野で博士号を取得しています。
〇読者への前置き
精神医学と心理学の二方面から人間関係を困難にする状況をゆっくり解説します。
高齢者 コミュニケーション
介護職者であれ、家族であれ、介護を受ける方と信頼関係を築くためには、コミュニケーションは必須であります。
また、認知症予防にもなります。
そのために、高齢者の方と接して、信頼を得てコミュニケーションを交わすことが大切です。
(高齢者の自尊心を傷つけない話はしました)
相手の情報を得る
家族であれば、このような情報を得ることは不要ですが、相手のことをあまりわからない時は、相手の情報収集から始めないといけません。
具体的には、氏名、置かれている環境、家族のこと、職歴、また、病気の有無、などです。
ただ、これらは話題の中でつながって出てくることが多いです。
例えば、「どんなお仕事をされていたのですか?」ときくと、話が進んで、家族や、置かれている環境の話に及ぶことがあります。

高齢者 コミュニケーション 話題
また、事前に得る(介護士の方は、フェイスシート、そうでないときは、他からの情報)場合もあります。
たとえば、趣味に「庭仕事」などがフェイスシートに書かれてあったり、近所の噂などを聞いたりした場合、そこから話を作れます。
好きな花とか、家庭菜園をやっていれば、「どんなものを作っているのか」とか、「庭仕事のやりがい」「苦労など」を聞いていけます。
そのような話題がないときは、天気の話、ニュースなどの話しも、導入として使えます。
「最近暑いですね。お身体大丈夫ですか?」「台風がまた、発生しましたね」でも良いと思います。
相手との関係者を結ぶきっかけになっていくと思います。
また、「出身地」などの話をすると、話が円滑に進むことにあります。
具体的には、出身地の名産やおいしいもの、祭りなどの伝統行事などです。また、人情や風情などを聞くと話が盛り上がったりします。
さらに好きな「食べ物」とか、食べ物に関するエピソードなども聞くと、おいしいものなので、話が弾むことがあります。
また、健康の話をすると、高齢者の共通の話題でもあるので、ツボにはまると話が進むこともありますが、相手の健康状態が悪い場合が話している途中に分かって、気まずい思いに囚われることもありましょう。
注意することは、相手がいままで出来ていたことができなくなって、イヤな思いに駆られていることにたち入らないようにすることです。
身体が衰弱して思うように、動かなくなってきて、庭仕事ができなくなったのに、そのことを根掘り葉掘り書くと、相手はイヤな気持ちになると思います。
言葉のほかに、相手の表情などを見て、それ以上たち入ると、人間関係が損なわれると感じた場合は、その話題に触れないほうがよろしいでしょう。
さらに、亡くなった人、ペットなどの話もはじめのころ控えた方がよろしいかもしれません。
ただ、信頼関係ができた場合は、悩みを聞くという形で、これらの話題に触れられると思います。
高齢者 コミュニケーション 気をつけること
話す速さに注意
高齢者の方と話すときは、「ゆっくりを心駆けること」が必要になります。
加齢とともに、認知機能が衰えていると、話すスピードについていけないことも考えられます。
また、年を重ねるごとに、高い周波数の声が聞きとえれなくなると言います。
ゆっくりと、理解できたかを確かめながら、低い声で話すことが大切です。
高齢者 コミュニケーション 非言語
相手に対して、言葉でない部分(身振り手振り、表情など)を使って、話を聞くということも、高齢者のコミュニケーションには大切なことです。
言葉で伝わらない、「あたたかさ」「親密さ」などが、それらによって伝わることがあります。
(あたたかさ・親密さは認知症の予防などにたいせつとの話は回想法のところでお話ししました。)
また、背中や肩、手の甲などに軽く触れるスキンシップを有効に使うと、「高齢者を支えている」とのメッセージが伝わります。ただ、女性の場合や、触れられることがイヤな人もいるので注意をしてください。
また、視線ですが、高齢者の方と話すときは、同じ高さになるように留意してください。これが、「あなたも私も同じ」との無言のメッセージを送ることにつながります。
高齢者 コミュニケーション 効果
コミュニケーションを工夫することで、「見当識障害」が良くなることもあります。
意識的に会話の中に、日時、季節、場所などを練り込んで話すとよいでしょう。
例えば、「お昼たべようか?」ではなく、「12時にお昼食べようか」と時間を練り込みます。「半袖に着替えよう」ではなく、「夏が来て厚いので半袖にしょう」と述べます。
たったこれだけの気配りなのですが、見当識機能が衰えるのを緩やかにできます(むろん、そうならない人もいます)。
まとめ
高齢者が認知症に陥る、一つの要素に、自宅に引きこもりになって、コミュニケーション不足があげられます。
家にいる高齢者の方を無理に外に連れ出すことはできません。
しかし、せめて、高齢者の方と接する機会がある場合は、明るく、優しく、相手を尊重して、信頼関係を深めるようなコミュニケーションのやり取りがのぞましいです。
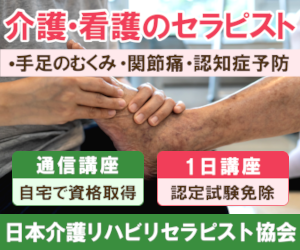
高齢者との接し方等々、学べる講座です。



