
昨日はレビー小体型認知症のお話しをしました。
レビー小体型認知症は、70歳半ばを過ぎた高齢者に多く見られます。
中核症状は、認知機能障害、幻視、パーキンソン症状などです。
また、初期はあまり症状が、目立つことはないです。嗅覚の異常、レム睡眠行動障害、便秘などが現れることが多いです。
その後、「起立性低血圧」からの立ちくらみや幻視やパーキンソン症状などが出てきます。嚥下障害もみられます。
進行の正確な知識を持ち、対応することが大切です。
本日は高齢者の生活習慣病です。
〇本日のテーマ 高齢者 生活習慣病
〇記事の信頼性
記事を書いている私は、心理学分野で博士号を取得しています。
〇読者への前置き
精神医学と心理学の二方面から人間関係を困難にする状況をゆっくり解説します。
高齢者 生活習慣病
生活習慣病とは
生活習慣病とは、疾患の原因が食事、運動、睡眠等などの生活習慣に関わって発症するものです。
さらに、慢性の腎臓病、肝硬変、慢性の閉塞性肺疾患、がんなども生活習慣病とされています。
最近は、認知症(アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、前頭側頭型認知症)やフレイルも生活習慣病に加えてよいと考えもなされています。
生活習慣病 糖尿病
前期高齢期の高血糖は糖尿病の合併症や死亡と関係します(中年も予備軍です)。
外国の研究では、75歳未満の糖尿病患者では、狭心症や心筋梗塞による死亡率が、(過去1〜2カ月の平均的血糖値を反映する)HbA1cが増えることで、増加するとされます。
ただ、75歳以上では、HbA1c値の増加と、心血管死亡リスクの増加がそれほど明確ではありません。(しかし、注意は必要です)。
逆に重症低血糖は年齢が上がるにつれて発症しやすくなります。

脂質異常症
前期高齢者でLDL(悪玉)コレステロールの値が高すぎると冠動脈疾患に陥る危険性があります。
ただ、75歳以上の高齢者では、LDLコレステロール値と冠動脈疾患との間に関係性が低いとの報告もあります(こちらも、注意は必要です)。
高血圧
高血圧を予防する降圧薬の投与により脳卒中、心不全、心血管病による死亡が少なくなります。
これは全ての年齢に見られた傾向で、生活習慣を改善しても、高血圧が改善されない場合、降圧剤による治療をするのが良いでしょう。
認知症発症
糖尿病とメタボ(メタボリックシンドローム)は認知症発症の危険が大きいと言われています。
糖尿病は中年・高齢者のいずれにおいても、認知症の危険リスクとなります。
また、高齢者の慢性炎症で発症のリスクが増えます。
メタボリックシンドロームになると、さらに認知機能が低下しやすいです(ただ、75歳以上の高齢者において、関係は明らかになっていません)。
高齢者が高血圧に陥った場合は、認知症との関連はないとされ報告もあります(但し、注意が必要です)。
ただし、動脈硬化症や、脳出血のリスクは大きいです。
生活習慣病 フレイル
ADL(Activities of Daily Living)とは「寝起き、移動,排せつ、入浴,食事,着替えなどの,日常生活に欠かせない最低限の動作で,高齢化や障害の程度をはかる指標」です。
ADLの低下は、認知機能、身体機能の低下、さらには社会環境、精神面の影響があるとされます。
高齢者の生活習慣病はADL低下の危険要因になります。糖尿病はADL低下が2倍近くになるとされます。
高齢期の肥満や、中年期からの肥満や身体の活動の低下は、高齢期のADL低下のリスクとなります。
また、サルコペニアと肥満が重なるとADL低下・転倒・骨折さらには、最悪の場合、死亡を将来しやすくなります。
生活習慣病 治療
上記したように、高齢者の生活習慣病は、認知機能が低下したり、ADLが低下するなどに陥ります。
特に糖尿病に罹患すると認知症、ADL低下のほか、サルコペニア、フレイル、低栄養などのリスクが増大します。
高齢者が生活習慣病に陥るとセルフケアが不可能になることから、介護者が薬の内服を手伝う必要に迫られます。
介護者の負担が増大すると介護者だけでなく、患者自身のQOLも低下したり、心理的な疲弊から治療を続けるのが難しくなったりします。
したがって、高齢期の生活習慣病では、
①血糖値、血圧、脂質のコントロールを図り、疾病に陥ったり、疾病を進行させないこと
②サイコぺニア、フレイル、認知症、うつ病などの防止をすること
③患者のQOLを維持・向上させ、患者や介護者の負担を減らすこと
生活習慣病 管理 治療
血 圧
高齢者の生活習慣病の管理目標値は年齢だけでなく、認知機能、ADL、有害事象のリスク、併存疾患、平均余命、社会サポートなどに設定することが多い。
高齢者の高血圧では、65歳から74歳では140/90mmHg以上の血圧レベルを降圧薬開始とし、管理する数値の目標も140/90mmHg未満とします。
75歳以上では150/90mmHgを当初の目標とし、忍容性により140/90mmHg未満を降圧目標とします。
脂質異常症
高齢者の脂質異常症のガイドラインでは、前期高齢者では成人と同様のLDLコレステロール管理方針を適応します。
75歳以上の後期高齢者の一次予防では、総合的な利益を考慮します。
二次予防については、肝臓におけるコレステロール合成を抑え、血中のLDL(悪玉)コレステロールを低下させるスタチン系薬の投与は有用であると考えられます。
高血圧または脂質異常症でフレイルが進んだ高齢者では管理目標は個別に検討することになります。
多くの疾患や機能の低下が存在すると、糖コントロール目標を高く設定します。多くの併存疾患があると、血糖コントロールの寿命延長効果が難しくなるからです。
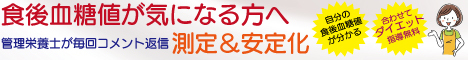
ADL、認知機能、併存疾患による死亡のリスクを推定しながら、柔軟な管理目標を設定することが、今後、糖尿病だけでなく、他の生活習慣病でも行われることが期待される。
高齢者生活習慣病の食事療法
高齢者の生活習慣病に関する食事療法は過栄養とともに、低栄養にも留意します。
低栄養に陥っているかは、食事摂る量が低下すること、体重減少、BMI低値に注意します。
体重の減少は生活習慣病の食事療法に関しては重要である。しかし、高齢者で食事療法により頼って減量するとサルコペニアを発症することがあります。
運動療法とともに運動療法を併用ことも大切です。
特にバランスのとれた食事を心がけ、炭水化物、タンパク質、脂肪が偏らないようにします。
ビタミン、ミネラル、食物繊維を十分にとります。
バランスの悪い食事は認知症やサイコぺニア発症の危険性が高まります。
塩分について
加齢により味覚が鈍くなり、塩分を過剰摂取していることもあります。味がしなくておいしくない料理から食事が進まなく低栄養になることもあります。
また、野菜や果実からとれるカリウムの摂取不足に注意をして、塩分を体外に出すことも視野に入れてください。
タンパク質
重症の腎機能障害の人はタンパク質の制限が加わることが多い。
一般の高齢者では、ある程度のタンパク質の摂らないと、筋肉を保つことが容易でなくなります。
低栄養の場合には、体重1キロにつき1.5g前後のタンパク質をとることが大切ともいわれています。
高齢者生活習慣病のタンパク質制限は、医師や栄養士の指導の下に行われることが必要です。
高齢者は、長年の食習慣から、食事を変えるのは困難を伴うことがあります。焦らずに、気持ちを考えながら、「食べても美味しくない」とい
高齢者生活習慣病の運動療法
食事療法とともに、運動療法は大切な治療です。まず身体の活動量の増大が大切な点です。
活動量の増大は認知機能低下の防止、血糖、血圧、中性脂肪の値をさげます。
また、逆にHDLコレステロール値の上昇、インスリン抵抗性を改善させます。
高齢者が行う運動の種類としては有酸素運動、筋肉運動、バランス運動、柔軟性運動などがある。
有酸素運動は糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満の治療として重要です。
筋力運動は、糖尿病やサルコペニア肥満の患者に対して行うと効果的とされます。また成長ホルモン(高齢者の方も分泌され、健康に大切です)も分泌されると言われています。
高強度の筋肉運動は筋肉量の増加、QOLの向上、インスリン抵抗性、血糖コントロールの改善をもたらします。
ただ、ご自分の年齢や体調を考えながら適切な運動を行うと良いでしよう。
日頃から、自分の身体の状態をチェックしておくことが大切です。




